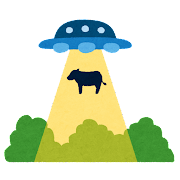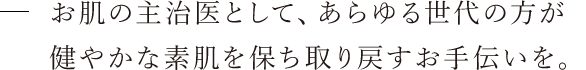紫外線にご注意を
晴天の日の紫外線が強くなっていて時には夏を感じることもあるくらいです。
紫外線は、単に日焼けやシミだけではなく、免疫機能の低下や、皮膚がんやそれに近い病気を引き起こすということもわかっています。
皮膚には以下のようにたくさんの役割があります。
❶バリア機能・・・紫外線・ほこり・乾燥などの外部刺激からの保護
❷体温調節・・・外界と体内の熱エネルギーをコントロールする
❸分泌排泄・・・皮脂や汗を分泌し塩分やアンモニアなどの老廃物を排泄
❹経皮吸収・・・薬剤などを表皮や毛穴から行なう ❺皮膚呼吸
❻免疫機能・・・異物や細菌など有害物質の侵入を防ぎ排除する
❼合成・・・日光浴により骨の形成に必要なビタミンDを合成、またコレステロールや保湿効果の高いセラミドも合成
❽感覚・・・温・冷・痛・圧・触覚の5つの感覚機能があり外部刺激を脳に伝える
日光にあたることによりビタミンDが生成されたり、特性を活かして光線療法(乾癬やアトピー性皮膚炎)に使われたりする紫外線ですが、悪い影響もたくさんあります。
≪紫外線による影響≫
◆急性的なもの
①日焼け
サンバーン(皮膚のやけど、真っ赤になり痛みを伴なう)
サンタン(サンバーン後数日して起こる、メラニン増加により黒くなる)
②免疫機能低下
③紫外線角膜炎
◆慢性的なもの
①シミ・しわ(光老化といわれる紫外線による障害で、年齢変化とはちがった変化)
②皮膚がん
③前がん症
④白内障などの目の病気
≪紫外線を効果的に避けるには≫
屋外では太陽からの直射光だけではなく、大気中の分子に当たって散乱した散乱光、直射光が壁や地面で反射した反射光の3方向からの紫外線を浴びることになります。 日傘や帽子も大切なアイテムですが、散乱光や反射光には効果がありません。サングラス、UVカットの洋服やスカーフ・手袋、日焼け止めなどが有効です。
≪日焼け止めの選び方≫
日常生活であればSPF20・PA+~++、外出や屋外活動ではSPF30~40・PA+++、特に日差しの強い中での活動や紫外線に弱いひとはSPF50・PA++++を目安としてください。顔はマスク着用でも油断せず全体に塗りましょう。
数値はあくまでも目安であり、ご自身の肌に合った使いやすいものをこまめに(2~3時間おき)塗り直すことが大切です。
❀いまの季節ですと、花粉やマスクによる肌荒れの状態で強い紫外線を浴びて顔の症状が悪化してしまうかたが多くいらっしゃいます。かゆみやヒリヒリ感があると保湿だけでは改善は難しいのではやめにご相談ください。
2024年5月23日11:15 AMアトピー性皮膚炎
アトピー性皮膚炎は、かゆみを伴なう湿疹がよくなったり悪くなったりを繰り返す皮膚の病気です。
この病気のかたは皮膚のバリア機能がもともと弱いため、外界からの刺激やアレルゲン(ホコリやダニなどのアレルギーを引き起こす物質)が入りこみやすく、それが原因となって炎症を引き起こします。さらに、かゆみを感じる神経が皮膚の表面にのびていて、かゆみに敏感になってしまいかくのを我慢できなくなります。こうしてかきこわしてしまいバリア機能が低下してしまうという悪循環に陥ります。
本人や家族が、アトピー性皮膚炎やアレルギー性鼻炎・結膜炎、気管支喘息を持っていたり、アレルギーを起こしやすい体質(IgE抗体を産生しやすい体質)のかたは、アトピー素因があるといえます。
【発症因子・悪化因子】
職場および日常生活がアレルゲン物質や刺激物にさらされる環境下であるかどうか、ご自身のライフスタイル、気候(温度・湿度)、皮膚の生理機能の変調などが、アトピー性皮膚炎の症状コントロールに関わってきます。
また、かゆみの誘発・悪化因子として、温熱寒冷、発汗、ウール繊維、精神ストレス、食事、飲酒、感冒などがあげられます。
【特徴・症状】
◇皮膚が全体的に乾燥し、湿疹は左右対称に現れることが多いのが特徴です。
◇年齢によって好発部位が異なります。
・乳児期・・・頭・頬・口周囲・首・耳のつけ根から、悪化すると身体や手足に広がる
・幼児・学童期・・・首・肘の内外、ひざとその裏側などの関節部分
・思春期・成人期・・・上半身(顔・首・胸・背中)
◇皮膚が乾燥してカサカサしている状態から、湿疹のあった部分が硬くゴワゴワしたり、赤く腫れてジクジクしたり、段階はさまざまです。
【治療の基本】
❶スキンケア
まず身体を清潔に保ちます。洗うときはゴシゴシこすらずシンプルな石けんやボディソープをよく泡立てて、手でなでるように洗いしっかりすすぎます。通常はこれでじゅうぶんです。傷やただれがあっても同様です。※界面活性剤不使用の石けん類を選び、ナイロンタオルは使わないようにします。
入浴・洗顔後は保湿ケアをしっかり行ないます。お肌のバリア機能を安定させ炎症を起きにくくします。炎症が起きなければかゆみも起きず、悪循環を起こさないため基本中の基本となります。
❷薬物療法
スキンケアだけではコントロールできない炎症やかゆみといった症状に合わせ、かゆみをおさえる抗ヒスタミンの飲み薬や炎症をおさえる塗り薬などを使います。
※飲み薬や塗り薬、スキンケアをきちんとしていても効果があらわれにくい重症なかたに当院では、症状に合わせて紫外線療法をおすすめすることがあります。また高額医療費制度対象の生物学的製剤などのご案内(他院紹介)をさせていただく場合もございます。
❸悪化因子対策
不規則な生活、寝不足、ストレス、身体の洗い方などを見直すことや、食物や環境アレルゲン(ハウスダスト・ダニ・カビ・動物上皮など)の検索と対策が必要です。
※アレルギーの血液検査は当院でも可能ですが、小さいお子様の採血は安全面を考慮させていただき、小児科での実施をお願いしています。
アトピー性皮膚炎の治療目標は、、、
①症状がない状態、あっても日常生活に支障がなく薬物療法をあまり必要としない状態
②軽い症状があっても、急に悪化することはなく、悪化しても長く続かない状態
この目標を達成するには、ご自身の日常のスキンケアと治療の継続が大切になります。
2023年11月24日11:30 AM
冬によくある皮膚のトラブル
空気が乾燥してくるとお肌のコンディションも夏とはまったくちがってきます。秋から冬にかけて起こりやすい皮膚のトラブルをご紹介します。いまから対策をして寒い季節を乗り越えましょう。
①乾燥
皮膚の角質層の水分量が減るとバリア機能の低下につながり、かゆみを引き起こす物質や細菌・ウィルスの侵入を容易にしてしまいます。かゆくて掻いていれば皮膚炎を起こしやすくなり、悪化すれば細菌感染など、事態は深刻になります。かゆくなるまえに保湿する習慣をつけましょう。
さらに乾燥はアトピー性皮膚炎や乾癬の症状悪化の原因にもなります。悪化予防のためには症状がない場合も日常的な保湿ケアが大切です。
②手荒れ・あかぎれ
冬場は水仕事の際にお湯を使うことが多いと思います。水と比べてお湯は皮脂を落としやすく、空気の乾燥も影響し夏よりも症状がひどくなります。水仕事以外でも乾燥した状態での手作業は、あらゆるものが刺激になって手を荒らしてしまい、ひどいと亀裂を生じるいわゆるあかぎれの状態となります。手作業の際は可能な限り手袋などで防御し、合間に保湿ケアをしましょう。
③しもやけ
しもやけは、大きな寒暖差で血管の収縮と拡張が繰り返されて起こる循環障害による皮膚の炎症で、かゆみや痛みを伴ないます。四肢末端をはじめ、頬や鼻先、耳などの血行が悪くなりやすく露出しがちな部位によく見られます。かゆみがひどくて掻きこわしたり、強い炎症から潰瘍になる恐れもあります。温めすぎるとかゆみや痛みが強くなることもあるので、まずは身体を冷やさない対策を心がけましょう。
④低温やけど
使い捨てカイロや簡易ヒーターなどをご使用になるときは、高温にもならないしお手頃だからと油断しないでください。40~50℃で心地よいと感じつつも無意識に長時間あてていると熱のダメージはじわじわと皮膚の深部に達し、気づいたときには重症で治りにくい状態になってしまいます。やけどを起こさないためにはカイロや器具による就寝中の保温はやめておきましょう。
冬のあいだは衣類をたくさん着込むせいか皮膚の変化に気づきにくいようです。とくに糖尿病のかたなど末梢神経障害がある場合、痛い冷たい熱いなどの感覚が鈍くなり、皮膚のダメージに気づかないまま症状が悪化するまで放置されてしまうことがあります。お肌の小さな変化にも早めに対処できるよう日頃からよく観察するようにしましょう。
2023年11月15日2:57 PMカビによる皮膚トラブル
湿気の多い暑い夏は、カビによる皮膚の病気が多くみられます。
◇白癬(いわゆる水虫)
白癬菌が皮膚の主に角質層に寄生して起こります。寄生した部分によって、足白癬(一般的な水虫)、爪白癬、手白癬、体部白癬、頭部白癬、股部白癬など名称が変わります。
手や足では、指の間に赤みや小さい水疱がぷつぷつあらわれたり、ふやけたり、はげしくむけて傷のようにジクジクしたりします。かゆみがないことも多いです。爪は厚みが出て白く濁ってもろくなってきます。体幹や四肢では特徴的なカサカサした輪っか状の紅斑が起こることがあります。
白癬菌は、素足で歩いたりスリッパを共用するような場所で感染が起こりやすくなります。じめじめしたところを好み強く生きる菌ですが、乾燥した場所や、ひとから剥がれ落ちた皮膚でもある程度生存できるといわれています。
水虫持ちの家族がいるご家庭、公衆浴場、プール、宿泊施設、飲食店の座敷、医療機関、職員寮、体育館、更衣室など、素足や靴下で不特定多数のひとが出入りする場所では白癬菌が存在すると考えたほうがよさそうです。
◇カンジダ症
ひとのからだにもともと常在するカンジダ菌が過剰に増えることで起こります。
・カンジダ性間擦疹(皮膚同士がこすれ合う部分に起こるかゆみや痛みを伴なう紅斑)
・指間カンジダ症(指間の赤みが拡大しびらん形成、水仕事従事者に多い)
・カンジダ性爪囲炎(爪周囲に発赤腫脹、水仕事従事者に多い)
・爪カンジダ症(爪の変形や肥厚など爪白癬と症状が似ている)
・口腔カンジダ症(口腔内や舌に白苔や炎症性の赤み、灼熱感や痛み)
・性器カンジダ症(膣や外陰部に発赤や白苔、亀頭や包皮に発赤や鱗屑)など、
湿気の多い暑さ、多汗、蒸れ、衣類の締めつけ、不衛生などに加え、免疫低下、肥満、糖尿病、妊娠、抗菌薬の使用などがカンジダ症の要因になります。
◇マラセチア感染症
ひとのからだにもともと常在するマラセチア菌が過剰に増えることで起こります。
・癜風(身体にまだら状にできる皮疹で、多汗、高温多湿の季節で思春期以降20~30歳代男女に多い)
・マラセチア毛包炎(思春期以降20~30歳代の背中や胸にできるニキビ様のブツブツ、毛穴でマラセチア菌が増殖して起こる)
・脂漏性皮膚炎(感染症というよりは湿疹の仲間)
≪治療と予防≫
①抗真菌薬の外用と、部位や範囲、症状によっては抗真菌薬の内服治療を行なうこともあります。病院で菌がいるかどうか検査をして治療を開始することをおすすめします。
②身体のあらゆる部位に発生することがあるため、特に暑い季節は毎日シャワーなどで身体を清潔に保ちましょう。汗は洗い流すのが効果的ですが毎回石けんを使う必要はありません。乾燥しすぎると肌のバリア機能が低下します。
③菌は高温多湿の環境を好み繁殖します。蒸れや汗などで湿った肌着や靴下は早めに交換し、清潔でドライなものを身につけるのが理想です。また密着度の高い衣類の締めつけや摩擦が起きる部分も菌の増殖を促しますので避けたほうがよさそうです。
④疑わしい症状がみられたり、菌の存在が確認されたときは、身近なひとに感染させないために、接触行為はもちろん、タオルやバスマット、スリッパなど患部に接触するものの共有も避けましょう。
手湿疹
手が荒れやすいかたといえば、水仕事、理容美容系、食品系、職人、工場、アパレル、紙系、保育、医療(順不同)など、さまざまなお仕事を思い浮かべられます。また近年では頻回な手洗いや手指消毒が習慣化され、空気が乾燥する冬だけでなく一年を通して手が荒れるようになってしまったかたも多いと思います。
手は身体のなかでいちばんダメージを負いやすいパーツと言っても過言ではありません。どんなにケアや治療をしていても、受けるダメージが上回ってしまえば症状はなかなか落ち着いてくれません。治らないとあきらめたりせず根気よくケアを続けることが大切です。
【手荒れ・手湿疹の症状と原因】
乾燥感やつっぱり感などの違和感から、徐々にかさつきやごわつきのある硬さが加わり、ひび割れや亀裂、あかぎれなどを生じて痛みを伴なうようになります。さらに赤いブツブツや水ぶくれ、じゅくじゅくした傷ができるようになります。
手洗いや薬品使用などにより、皮膚表面を覆う皮脂膜が取り除かれると、皮膚のバリア機能が低下して水分は失われ乾燥状態になります。バリア機能が低下した状態でさらに刺激を受け続けると、アレルゲンや細菌から身を守れずにどんどん症状は悪くなってしまいます。
また、アトピー性皮膚炎をお持ちのかたはもともと乾燥しやすい体質があるため、手の症状が起きやすくなっています。
【ケアと治療】
①うるおいでバリア機能を高める
まずはハンドクリームや保湿剤をこまめに塗り、乾燥させないことが第一歩です。手洗いの後はもちろん、何かをするたび、また、少しでも乾燥を自覚したら、そのつどそのつどで塗りましょう。どうせすぐに手洗いするからとは思わないでください。少しのかさつきでも塗りたくなるくらいになりましょう。
②あらゆる刺激から身を守る
さまざまな作業で刺激を受けてしまうのは生活上、職業上、避けて通れないことです。なるべくダメージを少なくおさえるために許可されている場面ではできるだけ手袋を使ってください。手袋での作業も何とか慣れてくるものです。手袋の着用を禁止されている作業の場合は、とにかくこまめにハンドクリームを塗りましょう。
③赤みやかゆみ、ブツブツやじゅくじゅく、痛みや亀裂は要治療
しっかり症状が現れたら保湿だけではもう間に合いません。くすりの力を借りて症状をしっかり治してしまいましょう。市販でも合っているものなら問題ありませんが、細菌感染の兆候などがないかも含めていちど診察を受けていただくと安心です。
汗とかゆみ
乾燥による皮膚炎に悩む季節が終わり、汗ばむ陽気の日が多くなってきました。汗も乾燥と同様に皮膚トラブルを起こしやすい要因のひとつです。
アトピー性皮膚炎などの慢性的な皮膚の病気をお持ちのかたはもちろん、普段から皮膚が健康なかたでも汗をかくとかゆみを感じることがあります。
≪原因≫
①あせも(汗疹)
たくさん汗をかいたところにできる湿疹で強いかゆみを伴ないます。汗に含まれる塩分や皮膚の表面の汚れなどで汗の通り道が塞がってしまい、汗がうまく排出されなくなり内部に溜まってポツポツ炎症を引き起こします。皮膚同士が重なり合いやすいところ、汗をかきやすく蒸れやすいところによくあらわれます。
②汗かぶれ
汗をかいた皮膚全体が、汗に含まれるアンモニアや塩分などの刺激で荒れてしまう症状です。普段からお肌のバリア機能が弱いアトピー性皮膚炎のかたや乾燥がちのかたは特に注意が必要です。あせものようなポツポツというよりは全体に赤くてかゆいのが特徴です。首まわりや脇、胸の下、肘・膝の裏側などの汗が溜まりやすいところによくあらわれます。
≪予防≫
◇かいた汗をそのままにせず、やさしくおさえて拭き取るか洗い流しましょう。ただし、洗うたびに石けんを使用すると乾燥の原因になりますのでぬるま湯で流す程度がおすすめです。
◇通気性のよいものや吸水性のある衣類を選び、ゴムやベルトの締めつけをなるべく避けましょう。汗で濡れた衣類は交換したほうがよいでしょう。
◇バリア機能を保つために普段からスキンケアを心がけましょう。また、春・夏・秋は紫外線が強くお肌へのダメージがバリア機能低下を招きます。UVケアも忘れないでください。
◇かゆくてもかかないようにお願いします。かき傷から細菌感染を起こすと蜂窩織炎やとびひなど重症化のリスクがあります。ポツポツや赤み・かゆみがしっかりあらわれたら予防策だけではおさまりません。なるべく早めにご相談ください。
かゆみ
皮膚トラブルのなかでも最もやっかいな症状のひとつにかゆみがあります。
かゆみは、皮膚に付着した異物を除去するために「掻く」という行動を起こさせる生体反応といわれていますが、「掻く」という行為は皮膚科的にはNGな行動です。
かゆいところを掻くことにより、爽快感を得られるので一時的に落ち着いたように感じます。ほんの一瞬、ひと掻き程度ですむようならNGとまでは言いません。ひと掻きしたことにより快感を得られると、さらに快感が欲しくなり、もっともっと搔きたくなります。
思いのままに皮膚を掻いてしまうと、
かゆい→掻く→皮膚が傷つく→皮膚のバリア機能を壊す→肌が過敏になる→炎症が起き悪化する→強いかゆみ→さらに掻く→さらに傷、、、
という悪循環が生まれ、このサイクルから離脱するのに苦労します。
≪かゆみがつらい皮膚の病気≫
◇じんましん
かゆみを伴なう赤みやふくらみが出たり消えたりを繰り返す。原因不明のことがほとんど。6週間未満で出なくなる急性じんましんとそれ以上に渡る慢性じんましんがある。
◇痒疹(ようしん)
虫刺されのようなボツボツしたもりあがりがいくつもできる。何らかの刺激に対する炎症反応が原因と考えられている。一時的なものと、いつまでも治らず硬いイボ状になるものもある。夜間眠れないほどの強いかゆみが特徴。
◇皮膚掻痒(そうよう)症
見ためは明らかな皮疹がないにもかかわらず強いかゆみがある。内科的な疾患が原因のことがある。乾燥肌を伴なうことが多い。掻くことにより皮膚症状(湿疹、皮膚の厚みや硬化、色素沈着)が出る。
≪予防と治療≫
①掻かない・・・掻き始めると止まらなくなります。悪循環のはじまりです。最初が肝心です。
②冷やす・・・保冷剤などをハンカチなどでくるんで患部にあててください。冷却シートなどを貼りつけるのは刺激になるのでやめましょう。
③スキンケア・・・保湿ケアを習慣にして、皮膚のバリア機能の低下を防ぎましょう。皮膚が乾燥しているとかゆみを感じやすくなります。また、紫外線予防も大切です。
④衣類や室温の調整・・・体が温まるとかゆみが増します。また、衣類に含まれる化学繊維がチクチク刺激になったり、ゴムの締めつけ感や縫い目によってかゆみを感じることもあります。汗の刺激もかゆみの原因になりえますので気温の変化に合わせて調節を。
⑤入浴方法・・・熱すぎない40℃以下で温まる、体のゴシゴシ洗いはしない、しっかり泡立てた石けんやボディソープの泡を使って、なでるように手で洗いましょう。体が温まるとかゆみは増すので長湯は控えましょう。 ⑥我慢できないかゆみやおさまらないじんましん、湿疹などの症状がしっかりあるときは、かゆみ止めの飲み薬や塗り薬を使って早めに治療を始めることで症状をこじらせずに済みますので、いつでもご相談ください。
湿疹・皮膚炎
ポツポツ赤く膨らんでかゆくなる皮膚の症状を、広く湿疹(皮膚炎も同じ意味)と呼びます。ジクジクやカサカサ、小さな水疱などを伴なうこともあります。
≪原因≫
外的要因・・・ハウスダストや花粉、洗剤や薬剤、細菌など体の外側からの要因
内的要因・・・体の調子や皮脂の状態、汗のかきかた、アトピー体質など個々で持つ要因
外的要因が皮膚から侵入すると、その異物を排除しようとする炎症反応が起こります。このときの症状の出かたや強さは、そのひとの内的要因によって左右されます。
外的要因と内的要因が互いに影響しあって最終的に湿疹を形成します。
≪原因がはっきりしている湿疹≫
◇接触皮膚炎→いわゆるかぶれ。外的物質による刺激によるもので、例えば、オムツ皮膚炎、手湿疹(手荒れ)、ギンナン皮膚炎、シイタケ皮膚炎など
◇アトピー性皮膚炎→皮膚のバリア機能が低下しやすく、かゆみを伴なう湿疹が主症状で、悪化と改善をくり返す
◇脂漏性皮膚炎→皮脂の分泌が多いところに出る、カサカサと赤みのある湿疹
◇貨幣状湿疹→別症状の湿疹から移行することが多い。見た目が貨幣の様で比較的大きめ。強いかゆみを伴なう
◇自家感作性皮膚炎→体の一部分で起きていた湿疹などが急激に悪化し、全身に小さなプツプツや赤みが多発。強いかゆみを伴なうことが多い
◇うっ滞性皮膚炎→静脈血流が滞り、赤みや湿疹が起こりやすくなる状態で、皮膚の委縮や硬化、落屑が起こり潰瘍などを生じやすい
◇皮脂欠乏性湿疹→乾燥してバリア機能が低下し、外的刺激を受けやすくなり湿疹やかゆみを生じる
◇汗疱・異汗性湿疹→手のひらや足のうらに小さな水疱がたくさんあらわれたり、広がって湿疹やかゆみも生じる
≪原因がはっきりしない湿疹≫ ※原因特定はできないものの、湿疹の多くは何らかの外的刺激によることが多い
◇急性湿疹→赤みや膨らみ、小さい水疱を伴なう、発症から数日しか経っていないもの
◇慢性湿疹→発症から一週間以上経っていて、慢性の経過から皮膚は厚みや硬さを伴なう
≪基本的な治療≫
①湿疹の原因がはっきりしている場合は、それを避けるようにする。
②適切なスキンケア・・・洗髪、洗顔、体、すべてにおいてゴシゴシ強いこすり洗いは厳禁です。泡をしっかり作ってやさしく洗います。乾燥に対しては保湿ケアをこまめにやさしくたっぷりと。
③塗り薬・・・塗るコツはすり込みすぎないようなじませるイメージで。当院でも塗り方を実践でご指導させていただきます。 ④飲み薬・・・強いかゆみがある場合は抗ヒスタミンの内服薬も有効です。普段他の病気に対してのまれているお薬の内容がわかるように、診察の際はお薬手帳があると便利です。
⑤絶対に掻かない・・・かゆい→掻く→バリア機能が壊れる→刺激に弱くなる→症状悪化→とてもかゆい→掻きまくる、、、というかゆみの悪循環が生まれます。冷やしたり別のことで気を紛らわせましょう。ほんのひと時でも意識をかゆみから切り離すことで我慢できるような気がしてきます。掻きたい欲望に打ち勝ちましょう。
光線(紫外線)治療を正式に導入しました。
紫外線治療は、紫外線の持つ免疫抑制作用を利用して、過剰に反応を起こしている皮膚の症状を沈静化させる治療方法です。皮膚の治療に有効で安全とされる波長の紫外線を、症状のある皮膚にピンポイントで照射できます。また、短時間の照射ですむので、外来で簡単に治療を受けられる利点もあります。
保険適用の治療です。3割負担の保険で1回に約1000円の費用で、照射頻度は週に1~2回が効果的です。
治療の適応がある病気は、乾癬、アトピー、掌蹠膿疱症、円形脱毛症、白斑、悪性リンパ腫などです。繰り返す手のひどい湿疹や痒疹などにも効果があります。
<副作用>
紫外線を照射するため軽い日焼け状態になります。照射して皮膚が赤くならない程度の照射量を患者さまごとに見極めていきます。治療後はご自宅で照射部位を観察していただき、赤くなるようなら次回診察時にご報告していただきます。まれに赤みが強く出たり水ぶくれを起こすこともあります。
<光線治療を受けてみたい場合は...>
塗り薬や飲み薬できちんと治療を続けているにもかかわらず、改善が乏しいと感じられているかたに追加できるおすすめの治療です。治療の適応があるかどうかは、症状の程度や今まで行なっていた治療などから医師が判断致します。初めていらっしゃる患者さまは、これまでの治療内容がわかる薬手帳などをご持参のうえ、いちどご相談ください。
2023年1月29日11:51 AM
しもやけ、やけど、寒いといろいろ要注意です
本格的な寒い冬がやってきて急激に気温が下がり、体や手足の冷えがつらいかたも多いことと思います。
つらい冷えに対して急激に強く温めてしまうと、しもやけを起こしていた場合、かゆみなどの症状がひどくなります。冷えた手足を温めることも大切ですが、まずは冷えないように徹底した防寒を心がけましょう。
しもやけについてくわしくはこちら→『しもやけにお悩みではありませんか?』
寒さに対し、さまざまな暖房器具や保温アイテムがあります。気軽に使える40~50℃程度の心地よいあったかグッズはとてもありがたく、多くのかたの冷えの味方になってくれます。
ところが、高温にならないからと油断してしまうのはとても怖いことです。心地よい温度でも皮膚の同じ部分に長時間接触させることで低温やけどを起こします。
使用中にかゆみや赤みが出てきたら使用を中止したほうがよいでしょう。
皮膚の違和感に気づきにくいお子さまや高齢者のかた、神経障害のあるかたや糖尿病のかたの使用は特に注意する必要があります。
低温やけどについてくわしくはこちら→『低温やけどを未然に防ぎましょう』
暖房器具や保温アイテム以外にもやけどの危険があるものはたくさんあります。
■電気便座の長時間の使用
■ヘアアイロンを床に置いたままにして踏んでしまう(周りのひとも巻き込む危険)
■熱い飲食物などの置き場所(小さいお子さまの運動能力を軽視してはいけません)
■カップめんを自分で用意してこぼす(わりと小中学生に多い)
■スマートフォンと充電器具(睡眠中、長時間無意識に触れている)
■アイロンや電気ケトル、ポットなどの使用前後の温度差、使う場所など
■ウォーターサーバー、IH調理器具、加湿器、バイクのマフラー、間接照明など、一見熱そうに見えないもの、熱いものであるという認知度の低いもの
万が一やけどしてしまったら、速やかに流水で冷やしてください。冷やすことでやけどの進行を防ぎ、痛みを和らげます。部位や範囲にもよりますが、流水で5分から30分くらいは冷やしましょう。 高齢者のかたやお子さまは、広い範囲を長時間冷やすことで低体温の危険もあるので注意が必要です。水ぶくれができたらご自身で破らずに受診することをおすすめします。衣服の上から受傷した場合は、無理に衣服を脱がずにそのまま流水で冷やして下さい。やけどしたところはだんだんに腫れてきますので、指輪などのアクセサリーは早めに外してください。
やけどは日ごとに症状の変化が起こり、治療もそれに合わせて変わっていきます。また、低温やけどの場合は時間がたって重症感が出てくることもあるので、なるべく早く医師の診察を受けることをおすすめします。
冬の寒さを安全に乗り切れるよう、また、さまざまな危険を察知し回避できるよう、日頃から気をつけて生活し、健やかに新年をおむかえください。
2022年12月29日11:18 AM