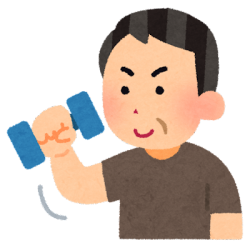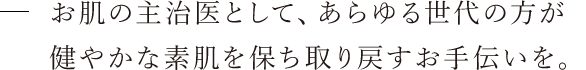水いぼの治療 ※塗り薬(自費)はじめました
水いぼは、伝染性軟属腫という皮膚の感染症で、主にお子さまがかかる病気です。
1~5ミリ程度の光沢のあるつぶつぶで、表面に小さなくぼみが見られ、中にある白い芯のような部分にウィルスが多く含まれています。
放置していても免疫ができれば自然に治る病気ですが、小さなお子さま同士のからだの接触でうつしあったり、擦れやすい部分で広がってしまうとやっかいです。
《当院で行なわれる治療》
❶ピンセットによる摘除(麻酔のテープを使うので予約制)
あらかじめ麻酔のテープを貼って1時間ほどおき、水いぼを直接つまみ取ります。つまみ取ったところはそれで治療完了(まれに芯が残ってしまうことあり)。
❷液体窒素による冷凍凝固療法
液体窒素をあて患部をやけど状態にし、皮膚組織を壊死させウィルスを死滅させる。1週間おきにくり返し行ない、ふくらみが平らになったら治療完了。
❸伝染性軟属腫専用保湿クリームによる外用治療(New)
殺菌効果の高い銀イオン配合クリームを1日2回塗る方法。2~3か月で治ると報告されている(個々が持つ免疫反応が大きく関与するとのことで、効果と治癒までの期間には個人差があり)。
※M-BFクリーム 15g 2200円 自費購入になります。

❹自然治癒を待つ
他のお子さまとの接触やかきむしる習慣がほとんどないお子さまは広がるリスクが少ないので、自然に治るのを待つ選択もありです。感染予防のためには皮膚のバリア機能が重要なので、保湿を心がけましょう。
治療を希望される場合は、水いぼが大きくなりすぎたり、たくさん増えたりするまえに早めにご相談ください。
2022年12月5日4:05 PM
夏のかゆみと対処法
❶汗によるかゆみ
汗をかいたあとにそのままにしていると、汗に含まれる塩分などの成分が刺激となりかゆみを引き起こします。かゆくてかいていると湿疹の原因にもなり、かきこわせば細菌感染のおそれもあります。
⇒汗は速やかに拭きましょう。乾いたタオルでゴシゴシこすると皮膚を傷つけます。帰宅時はすぐにシャワーで洗い流すようにします。出先ではおしぼりなどの濡らしたタオルで優しく押さえて汗を拭くようにしましょう。
❷虫や植物によるかゆみ
蚊やブユ、アブ、蜂、毛虫などの虫や、植物による皮膚トラブルも多く起こります。日常生活以外にも、レジャーで訪れる緑豊かな公園や山など、接触する機会が多くなるからです。
⇒虫が多く出るところに行く際は事前に対策をしましょう。肌の露出を最小限にしたり、虫よけスプレーを活用します。また香水などの強いにおいに対し蜂が攻撃してくることもあるようです。自然が多い場所では避けたほうがよさそうです。
もし虫に刺されたら、軽いものなら市販薬でよくなりますが、掻き壊してしまうほどかゆみが強かったり、すごく腫れてしまうなど症状がひどい場合は、早めに受診しましょう。患部は冷やしたり石けんで洗って清潔にしてください。
❸日焼け
夏の日差しは刺激が強いので、肌の露出に注意が必要です。日焼けにより皮膚の炎症が起こってかゆみが生じます。日焼けはひどくなると立派なやけどです。また紫外線は免疫力を低下させてしまいます。
⇒日焼け止めを塗る、羽織るものを用意しておくなど、レジャーはもちろんですが、紫外線対策は日常的に行ないましょう。日焼け止めはこまめに塗り直さなければいけません。ほんの短時間の露出でも紫外線はお肌に影響をおよぼします。また日傘やアームカバー、帽子などの併用も有効です。
日焼け後は、冷やして保湿しましょう。ゴシゴシこすったりさすったりしないでください。
赤みが強すぎるとき、かゆみや痛みが強いとき、水ぶくれが起こるときなどは早めに受診しましょう。
❹乾燥
猛暑の日々のエアコンは必須です。エアコンのきいた室内で過ごしていただくのが大切です。涼しいおかげで室内は乾燥気味です。また、塩素などを含んだプールの水や日焼け、レジャー施設での手指消毒など、乾燥の原因はたくさんあります。夏も乾燥に注意しましょう。
⇒保湿が必要ですが、暑いなか油分たっぷりのクリームを塗ると少し不快に感じるかもしれません。化粧水や乳液タイプのさらっと塗れる保湿を継続することが大切です。
❺慢性のかゆみ
アトピー性皮膚炎や慢性じんましんなど、慢性的な皮膚の病気は、夏の暑さや発汗、ストレスなどで悪化することが多くあります。
⇒❶~❹の対策をしっかり行なうほか、お薬を切らさないよう計画的に通院しましょう。
皮膚トラブルを予防して、暑い夏を楽しく乗り切りましょう。
2022年8月8日6:12 PM
酒さ
酒さは、“赤ら顔”ともよばれ、鼻や頬、額などに、赤みやニキビのような症状がでる病気です。30~50才代で発症しやすく、女性に多い傾向があります。
≪酒さの種類と症状≫
①紅斑毛細血管拡張型
・顔の赤み
・毛細血管の広がり
②丘疹膿疱型
・赤い盛り上がり
・膿をもったブツブツ
③鼻瘤
・鼻の皮膚が厚くなり、こぶのようなものができる
その他に、ほてりやヒリヒリ感、皮膚の乾燥やむくみ、眼の充血やかゆみが起こることもあります。
≪酒さの原因≫
明らかになっていません。暑さや寒さ、日光などの外的要因や、精神的ストレスや食べ物など体の内的要因などが重なって起きるといわれています。
酒さの症状を悪化させてしまう原因は以下の通りです。
●日光、高いまたは低い気温や室温
●熱いお風呂
●激しい運動
●ストレス
●医薬品、化粧品
●アルコール、香辛料 など
≪酒さの治療と予防≫
①治療
顔の赤みやブツブツに対し、内服薬や外用薬で治療します。
※以前は保険適応外だった塗り薬が保険でお出しできるようになりました。
また、保険外ですが毛細血管拡張に対してレーザーによる治療も可能です(当院では行っておりません)
②悪化因子を取り除く
悪化因子は、ひとつだったり複数だったり、ひとによってさまざまです。ご自身の悪化因子を見つけて、とにかく避けましょう。
③スキンケア
皮膚を清潔に保ち、悪化の原因となる乾燥や紫外線を防ぐことが大切です。
◆洗顔・・・ぬるま湯でやさしく洗い、タオルでこすらず押し当てるように水気をとる
◆保湿・・・乾燥は症状悪化のもと、保湿をじゅうぶんに
◆紫外線対策・・・帽子や日傘、日焼け止めで日常的に対策を
◆スキンケア用品・・・刺激の少ないもの
酒さは、よくなったり悪くなったりをくり返します。日常の中の悪化因子をうまく避け、根気よくケアすることでよい状態を維持できるよう心がけましょう。
2022年7月10日10:20 AM
梅毒
梅毒は、梅毒トレポネーマという細菌による感染症で、さまざまな性交渉で感染します。感染していても無症状であったり、症状が軽くて病気の自覚がないことがあるので、気づかないうちに感染させてしまっていることも多い病気です。
検査や治療が遅れたり、治療せずに放置したりすると脳や心臓に重大な合併症を起こすことがあります。
【梅毒の症状】 ※症状出現や消失の時期は個人差が大きく出ます
第1期
感染後、約1か月で感染部位(性器、肛門、口など)に、できもの、しこり、ただれなどができたり、また、リンパ節が腫れることもあります。治療をしなくても数週間で症状は消えてしまいます。
第2期
感染から3か月程度たつと、手の平や足の裏など全身に発疹ができます。ほかの病気と紛らわしい様々な種類の発疹形態(バラ疹・丘疹・粘膜疹・扁平コンジローマなど)や乾癬のような皮疹、脱毛などの出現もあります。
治療をしなくても数週間で症状が消える場合もあり、また、再発を繰り返すこともあります。症状がなくなっても梅毒トレポネーマは体内に存在し続けます。
晩期梅毒(第3期・第4期)
無治療の場合、感染から数年で、皮膚や筋肉、骨にゴムのような腫瘍(ゴム腫)が現れることがあります。また、心臓、血管、神経などに病変が生じ、場合によっては死に至るケースもあります。
【感染経路】
菌を排出している感染者との粘膜や皮膚の接触を伴なう性交渉で感染します。妊娠中に感染すると、胎児に感染させる可能性があります。
【検査】
医師による診察と血液検査で診断されます。検査は、感染機会から時間が経って陽性を示すようになるため、通常は感染したと思われる時期から3~4週間以上あけて行ないます。
【治療】
抗菌薬が有効ですが、菌を死滅させる効果はあっても、臓器などに生じた障害を元に戻す効果はないので、早期の治療が大切です。パートナーも検査を受け、感染していたら治療することが重要です。
梅毒に感染した人の血液中には抗体が存在しますが、再感染を予防できるものではありません。感染者との性交渉があれば再び感染のリスクはあります。コンドームの使用(100%と過信しない)やパートナーの検査や治療などの予防策は必須です。
梅毒は感染しても症状が出ない人もいます。検査を受けないと感染したかどうかは分かりません。気になることがある場合は、検査を受けましょう。
2022年6月1日9:23 AM
春に気をつけたいお肌のこと
気候の変化や生活環境の変化に伴ない、お肌の調子が悪くなりやすい季節です。ニキビや湿疹、乾燥など、もともとお困りのかたも症状が悪化してしまうなど、大小さまざまな悩みをお持ちではないでしょうか。
~春に多いお肌の症状~
①乾燥
②顔のかゆみ、ヒリヒリ感、湿疹
③ニキビ
④アトピー性皮膚炎の悪化
⑤じんましん
~春の肌トラブルの原因~
①花粉・・・目や鼻の症状がなくても、露出部分の顔や首にたくさんの花粉が付着することにより、かゆみや赤み、湿疹を引き起こします。
②PM2,5・・・通年舞っていますが春先に観測値が高くなるといわれています。これも花粉と同様に肌を刺激する要因です。
③紫外線・・・冬のあいだは気にならない紫外線も3月ごろから強まります。
④気温差・・・寒暖差にお肌が対応できずバリア機能が乱れてしまいます。
⑤ストレス・・・新生活のスタートによりストレスを感じやすくなります。ホルモンバランスや自律神経が乱れるきっかけとなり、お肌の調子を崩します。
~春のスキンケア~
✿花粉対策
メガネやマスク、帽子やスカーフを活用し、露出部位を最小限に。帰宅したら、衣類の花粉を払い落とし、速やかに洗顔をしてお肌についた花粉を落としましょう。
✿クレンジングや洗顔
たっぷり使ってやさしくなで洗いが基本です。洗顔料はしっかりたっぷり泡を立てて使いましょう。ゴシゴシ洗いは絶対NGです。
✿保湿
乾燥するとバリア機能が低下してしまいます。
✿UVケア
紫外線は皮膚の炎症を引き起こしたり、シミやシワの原因にもなります。ちょっとした外出時も油断大敵です。
✿バランスの良い食事、特にたんぱく質や緑黄色野菜を積極的に。
✿ストレス解消と睡眠時間の確保を心がけましょう。
春という季節もあっというまに過ぎ、夏の暑さがすぐにやってきます。汗をかいたり冷房の乾燥にさらされたり、夏には夏の肌トラブルがあります。保湿やUVケアはスキンケアの基本です。夏への備えにもなるので習慣にしてしまいましょう。
2022年4月14日9:47 AM毛穴の黒ずみを予防する
毛穴の黒ずみを気にされているかたは多いと思いますが、黒ずみの原因をご存じでしょうか?
肌はターンオーバーを繰り返し古い角質がはがれ、新しい角質に生まれ変わります。しかし睡眠不足や偏った食生活をしているとターンオーバーのリズムが乱れ、古い角質がはがれ落ちずに残った状態になります。また過剰に分泌された皮脂が混ざり合い角栓ができ、さらに洗顔やクレンジングで落としきれなかった汚れも毛穴につまっていきます。
毛穴につまった角栓が酸化して黒くなりポツポツと目立つ黒ずみになります。
皮膚表面の汚れや過剰な皮脂をケアすることにより、ターンオーバーを正常に機能させることが重要になります。
~セルフで行なう正しいケア~
◇クレンジング(メイクをされるかた)◇
❶しっかりメイクのときはオイルクレンジング、ナチュラルメイクにはリキッドタイプ、さっぱり好みのかたはジェルタイプ、しっとり好きにはミルクタイプ、など、メーカーによって種類はさまざまです。メイクのしかたやお肌のタイプに合わせてクレンジングを選びましょう。
❷使用量を守りましょう。少ない量ではお肌と手のあいだに摩擦が生まれてしまいます。じゅうぶんな量を優しい力加減でなじませます。こするのではなくなじませます。
❸なじませ残しのないよう、時間をかけすぎずになじませたら、ひと肌程度のぬるま湯で、クレンジング成分のすすぎ残しがないように流しましょう。
◇洗顔◇ 角質ケア石けんスキンピールバーのご紹介
❶泡立ちをよくするため、まずは手を洗い、顔を水かぬるま湯で濡らしましょう。乾いた肌に直接洗顔料をつけると、デリケートな肌の負担になったり、泡がすぐに消失してしまいます。
❷洗顔料をしっかり泡立てます。水と空気を少しずつ含ませながら、きめの細かい弾力のある泡をたっぷりつくりましょう。
❸泡を転がすように洗顔します。ゴシゴシこすり洗いはNGです。皮脂量の多い小鼻やTゾーンは丁寧に。
❹ぬめりがなくなるまでぬるま湯で丁寧にすすぎましょう。
❺やさしくおさえるように水分を拭き取ります。
◇スキンケアと紫外線対策◇
❶洗顔後はしっかり保湿しましょう。肌の乾燥はターンオーバーが乱れたり毛穴が開く原因になることも。
❷紫外線はメラニンを生成し毛穴の入り口が黒ずむ原因となります。一年を通して日焼け対策することをおすすめします。
◇日常生活◇
❶栄養バランスのとれた食事が大切ですが、特にターンオーバーを整えるビタミンAや、皮脂の分泌を調節するビタミンB2・B6、抗酸化作用や美白作用など美肌には欠かせないビタミンCを積極的に摂りましょう。サプリメントで補うのも方法のひとつです。
❷血行不良はターンオーバーの乱れにつながります。適度に身体を動かしましょう。
❸お肌のターンオーバーは睡眠中に活発に行なわれています。質の良い睡眠を心がけましょう。
❹ストレスもお肌の大敵です。ストレスのせいでホルモンバランスが乱れると、ターンオーバーが乱れたり毛穴が開いたりしてしまいます。
ご自身で実践できる毛穴のケアについてご紹介しましたが、プラスワンのアイテムをご紹介します。
グラファC10ローションは医療機関のみの取扱い商品です。
あらゆるお肌のお悩みにおすすめしたい化粧水です。サンプルのご用意もありますのでお気軽にご相談ください。
※アトピー性皮膚炎など皮膚科的治療をされているかたは主治医の指導のもとお使いください。
2022年2月3日5:02 PM
冬の皮膚トラブル
冬になると、寒さや空気の乾燥が原因の皮膚トラブルが起こります。トラブルの原因を知り、スキンケアや適切な保温アイテムの使用を心がけ、皮膚の健康を守りましょう。
❶乾燥肌
空気の乾燥によりお肌もカサカサしてきます。乾燥するとかゆみも伴ない、かいているうちにバリア機能が低下し、アレルゲンや菌、ウィルスなどの侵入を許してしまいます。さらにかゆみが強くなってかいてしまうことで湿疹化のリスクも高まります。※くわしくは⇒乾燥肌について
❷あかぎれ
乾燥したりお湯を使うことが多くなると皮脂や皮膚の水分が失われ、主に手足の皮膚がひび割れてきます。ひび割れが深くなって出血や痛みが出てくることもあります。手洗いや水仕事など石けんや洗剤の刺激も原因のひとつになります。冷えと乾燥を防ぐため、外出時の保護・保温、手作業や水仕事中の保護のため、手袋を有効に活用し、こまめに保湿ケアをしましょう。あかぎれ状態になると保湿だけでは治りませんので、早めの受診をおすすめします。
❸口唇炎
口唇も皮膚と同じく乾燥します。いまはマスクをしていることが多く、口唇が外気に触れる機会は少ないかもしれませんが、マスク内の蒸れにより荒れやすくなっています。また、マスク装着によりリップクリームをこまめに塗れなくなるため、乾燥がちになると口唇炎を起こしやすくなります。※⇒口唇のケアについて
❹しもやけ
血行障害が原因で手や足に起こる冬の代表的な疾患です。赤く腫れたりかゆくなったりします。悪化すると皮膚潰瘍に陥るのであなどってはいけません。※⇒しもやけについて
❺低温やけど
湯たんぽや電気カーペット、使い捨てカイロなどの使用によるやけどで、低めの温度でも長時間使用し続けることで生じる恐れがあります。熱いと感じたらすぐに使用をやめることで予防できますが、使用したまま入眠してしまうとやけどを起こすリスクが高まります。※⇒低温やけどについて
お困りのかたはいつでもご相談ください。症状がひどくないうちに治療することが大切です。
2022年1月6日12:05 PM
お肌の乾燥
冬は大気が乾燥するのでお肌の乾燥が目立ってきます。
≪乾燥肌のメカニズム≫
皮膚の表面は、表皮と呼ばれる細胞の層があり、いちばん外側に角層が存在しています。角層は皮膚のバリア機能(外部の刺激や異物から肌を守りつつ水分を閉じ込めておく機能)の役割を担っているほか、水分を保持して皮膚をみずみずしくなめらかに保ってくれています。角層の水分量の低下した状態が乾燥肌です。
もともと乾燥しやすい体質ではないかたも、冬や冷暖房のきいた室内は湿度が低く乾燥しており、お肌も乾燥しやすくなります。また、ほこりや花粉、紫外線、加齢なども乾燥の原因となります。カサカサ感や入浴後のつっぱり感、粉をふく、かゆみなどがあると乾燥肌といえます。
≪乾燥肌の予防はスキンケア≫
❶スキンケアアイテム
スキンケア用品は市販でもたくさん種類があります。形状や効能のほか香りを楽しむものなどさまざまです。スキンケアの基本は継続することです。まずは、ご自身にあったもの、塗りやすく続けやすいものを使うことをおすすめします。
お肌が弱く市販のもので合うものを見つけられないお困りのかたは、こちらでも処方やご紹介が可能ですのでご相談ください。
❷タイミング
顔や体は朝晩しっかりケアできるとよいと思います。最低でもお風呂上がりは必ずケアが必要です。入浴後はお肌の水分が失われやすいので、衣服を着る前に一気に塗ってしまうのがおすすめです。
手の場合は、頻回に洗ったり水仕事や手作業など刺激を受けやすいので、手洗いやひと仕事終えるたびにハンドクリームを塗る習慣をつけることが大切です。
❸刺激をあたえない
身体を洗ったりお化粧を落としたりする際にゴシゴシこすらないこと、また、スキンケアの際にもすりすり摩擦を与えながら塗らないことを心がけましょう。
お肌に何かを塗る際は、優しくなでるように塗り、表面に、ある程度のべたべた感が残った状態で終えましょう。(ティッシュが張りついて落ちない程度が目安です)
乾燥肌を放っておくと・・・
バリア機能が低下してしまい、ちょっとした刺激にも弱くなったり細菌が侵入しやすくなり皮膚炎を引き起こす、皮膚炎のせいでかゆみが強くなり、かいてしまうとさらに荒れて症状は悪化、、、と負の連鎖が始まります。
また、乾燥肌は皮脂がつまりやすくなっているのでニキビの原因にもなります。さらに水分と皮脂が少ない状態なので、肌を守ろうとして角質が固くなり、シワの原因にもなりえます。
乾燥肌は、こじらせてしまい皮膚炎にまで発展してしまうとなかなか自力では治せないものです。たかが乾燥と楽観視せず、早めにご相談いただけたら幸いです。
2021年12月8日3:56 PM
ニンニク注射(アリナミンF)はじめました
ニンニク注射には激しい運動後のビタミンB1補給や、ビタミンB1の欠乏による一般的な疲労に対する回復効果があります。
実際にニンニクが原料になっているわけではなく、ニンニクのにおいのもととなるアリシン化合物に由来する成分が含まれていること、薬剤自体のにおいが似ていることからそう呼ばれています。注射すると一時的に呼気や汗からにおいを感じられますが、一定時間経過すれば消失します。
◆効果・効能◆
・ビタミンB1欠乏予防
・ビタミンB1補給
・ビタミンB1欠乏による疲れ・代謝障害(神経痛・筋肉痛・便秘など)の改善
※効果には個人差があります。
疲れがたまっても仕事を休めないかた、この1週間ががんばり時だというかた、ハードな運動をしていて筋肉疲労がつらいかたにすすめられます。
◆用法および注意事項◆
1回量20mlをゆっくり静脈注射します。注射後すぐににおいを感じます。
※まれに血管痛や手のしびれを感じる場合があります。
◆副作用◆
血管痛、注射部位の硬結・痛み、発疹・掻痒感などの過敏症、ショック(0.1%未満)
◆金額◆
1回1アンプル(20ml) 1000円
※効果の持続期間は個人差によりますが、3日~1週間ほどとなっていますので、週に1~2回を目安に注射をおすすめします。
2021年10月26日10:15 AM
ウオノメかな?それはイボかもしれません
足の裏にできているかたいマメのようなできもの、靴があたったり歩くと痛かったりして、ウオノメができてしまったと放っておいてはいませんか?しかも、かたくなったところをご自身で爪切りやカッターナイフを使って切り取っていませんか?
ウオノメであれば前述のように物理的に除去するか、かたくならないように工夫(靴や中敷きの見直しなど)することが治療になりますので、ご自身でやってみるのも悪くありません。
ところが、何年もウオノメと思っていたものが実はイボだったというケースはたくさんあります。
―かたいところを削ったら痛くもないのに血が出てきたことがある
―お子さまの足の裏にウオノメがあるなと思ってはいるが様子を見ている
この場合、イボの可能性が高いです。ウィルス性の疣贅(ゆうぜい)ともいいます。
足だけでなく手にできることも多く、身体のほかの部分にもできます。
イボを治すには液体窒素による凍結療法が有効で、保険がきくポピュラーな方法です。自然に治るケースもありますが、治るのを待っているうちに数が増えたり大きくなったりしてしまい、治療に要する期間も長くなってしまいます。大人の場合は年単位で治療することも。。。
いぼの治療は、できてから早期に治療を開始できるかが大変重要です。
怪しいものを見つけたら早めにご相談ください。
2021年10月20日12:37 PM








![image0[243]](http://www.machihifu.com/wp-content/uploads/2021/08/image0243-250x333.jpeg)