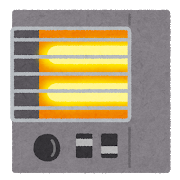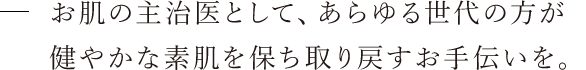くちびるのケアについて
乾燥による肌トラブルの起こりやすいこの季節、口唇のケアもスキンケア同様大切になってきます。
口唇の表面がカサつきひび割れたり、炎症を起こして腫れたり湿疹ができる、これを口唇炎といいます。口唇炎がひどくなると痛みが生じたり傷ができたり、カビがついたり、細菌感染を起こすなど悪化することがあります。
原因は、、、
★環境によるもの(寒さ、乾燥、紫外線など)
★かぶれ(化粧品、リップクリーム、歯みがき、歯科治療など)
★喫煙や食事
★体調不良
予防のしかたは、、、
❶口唇を湿らせようと舐めてはいけません。唾液には消化酵素が含まれており、なめることが刺激となってしまいます。お子さまの場合は甜めグセによる舌なめずり皮膚炎が起こってしまうこともあります。乾燥を気にするようならリップクリームを有効に取り入れましょう。
❷乾燥させないよう保湿しましょう。部屋の加湿も大切です。また、市販のリップクリームが合わないかたはご相談ください。
❸生活習慣の乱れにより肌あれが起こるのと同様に、口唇へも影響があるといえます。じゅうぶんな睡眠やバランスのよい食生活を意識しましょう。
治療は、、、
軽い症状であれば保湿剤によるケアが中心となります。さらに、かゆみや症状の強さに応じてステロイドの外用薬や、場合によっては抗アレルギーの内服薬を使用することもあります。
ご自身では口唇炎と思っていても、なかなか治らないようなら別の病気が隠れているかもしれません。口唇ヘルペスやカンジダ症のほか、全く別の疾患に伴なう口唇の症状であることも。治りが悪いときは受診をおすすめいたします。
2020年1月29日10:33 AMしもやけにお悩みではありませんか?
本格的に寒くなりました。すでに手足の凍るような冷えに悩まされているかたも多いことでしょう。そんな冷えから毎年しもやけになってしまうと来院されるかたも増えています。
しもやけは、寒暖差が大きくなることで血管の収縮と拡張が繰り返されて起こる、血液の循環障害による皮膚の炎症です。四肢末端をはじめ、頬や鼻先、耳などの血行が悪くなりやすく露出しがちな部位によく見られます。
症状は、ジンジンとした感覚、かゆみや痛み、熱感とともに赤い発疹や水疱・しこりが現れるタイプと、手足が真っ赤になるタイプがあります。また患部が温まるとかゆみや痛みが強まるのも特徴です。
〜しもやけを予防するには〜
しもやけになるのは体質によるところもあるため、症状がひどくならないように心がけることが大切です。
❶しっかり保温する
寒い季節の外出時は手袋や耳あて、帽子などの防寒具で冷えを防ぎましょう。カイロなどで熱を加えるとかゆみなどの症状が強くなってしまいます。
❷手足のむれや拭き残しの水分に注意
靴下が雨や汗などで濡れているとその水分が皮膚表面を冷やし、しもやけの原因となります。湿った靴下はすみやかにはきかえたり、5本指ソックスをはくなど、保温と同時に通気面を考慮しましょう。また手洗い後は水気をきちんと拭きましょう。
❸血流を妨げないよう、きつい靴や先端の細い靴は避けましょう。
❹生活習慣を見直す
バランスのよい食事、特にビタミンE(毛細血管をひろげ血行をよくする働き)やビタミンC(ビタミンEの働きを助ける)の摂取を意識してみましょう。また、睡眠不足は血流を悪くします。良質な睡眠と適度な運動を心がけましょう。
治療は、ビタミンEや血行を改善する外用薬のほか、症状に合わせてビタミンEなどの内服薬を使うこともあります。かゆみがひどくて掻きこわしたり、強い炎症から潰瘍になるおそれもあります。症状にお悩みのかたはいちどご相談ください。
2019年12月4日10:02 AM
ささくれ、気になりますね
本格的に寒い季節の訪れを感じ始めてまいりました。寒くなってくると皮膚科的には、乾燥肌やそれに伴う湿疹、手荒れ、低温やけど、しもやけなど冬ならではの症状のかたが増えてきます。
ほんの小さく、ささいな皮膚の症状にもかかわらず、こじらせるととんでもなく厄介なものになりかねない『ささくれ』についてお話ししたいと思います。
ささくれは、部分的に爪まわりの皮膚が剥けている状態で、どなたにも経験があるものです。手に限らず足指になることもあります。
原因は乾燥です。乾燥により外的刺激に弱くなり、ちょっとしたことで剥けやすい状態になっています。また、たんぱく質やビタミン・ミネラル不足も関係しているようです。さらにお子さまは爪を噛むクセがあると乾燥を招きやすいので注意が必要です。
ほんの少し剥けているくらいでも気になりだすと放っておけない、なんとかしたい、ついついさわっちゃう、気になる、ずっとさわっちゃう、そして、自分でむしっちゃおう!というかた、たくさんいらっしゃることでしょう。
いけません。その部分が傷になります。バイ菌がつきます。腫れて痛いです。膿んでしまいます。膿がたまってしまいます。こうなると切開して膿を出す処置であったり、抗生物質の内服や外用薬が必要になりますので受診をおすすめします。
また、ささくれを剥いたその傷にイボのウィルスがつくとイボができてしまう恐れもあります。ささくれ部分が多数あるとそれぞれがイボになってしまうかもしれません。
自ら傷をつくり外界の菌やウィルスを容易に受け入れる状態にしていること、おわかりいただけましたでしょうか?
乾燥させないようこまめに保湿していただき、ささくれを予防していきましょう。
2019年11月22日10:40 AM蜂に刺されたら
蜂のなかでも刺すものとして一般的なのがミツバチ、アシナガバチ、スズメバチで、なかでも後者の2種は庭木の手入れやハイキングの際に多くみられ、特に秋の野山での野外活動では要注意です。
蜂はこちらから刺激しなければ攻撃してくることはありません。
自宅でも洗濯物を取り込むときなど注意し、万が一家に入ってしまっても追い払ったりせず、明るい方の窓や扉をあけ、自然に出ていくのを静かに待ちましょう。
蜂に刺されたときの応急処置
❶流水で患部を冷やしながら洗います。ハチ毒は水に溶けやすく薄める効果があり、また冷やすことで腫れと毒のまわりをおさえます。針が刺さったままの場合は、可能であればピンセットなどで静かに抜きましょう。
❷指で患部をつまみ、毒をしぼり出します。このとき口で吸いだすのNGです。
❸患部を保冷剤などで冷やし、ステロイドや抗ヒスタミンの外用薬があればひとまず塗っておくとよいでしょう。
❹30分は安静に過ごしていただきます。
刺されてから15分間程度で急激にじんましんやかゆみなどの皮膚症状、動悸、冷や汗、胸部圧迫感、喉のつかえや息苦しさ、腹痛、下痢・嘔吐などが起きるようならアレルギー反応と考えすみやかに救急要請をする必要があります。重篤なものはアナフィラキシーショックとよばれ血圧低下や呼吸困難、意識障害を起こし、死に至ることもあります。
蜂に2回刺されたら危険といわれますが、1回目だから安心というわけではなく、最初から強いアレルギー症状を起こすこともありえます。蜂に刺されたら注意深く観察しつつ、異変があれば救急病院を受診しましょう。
2019年10月31日6:47 PM汗とお肌
夏の暑さに汗はつきものです。脱水や熱中症、皮膚科的には肌荒れやあせもの心配があり、汗はかかないほうがよいと思われがちです。
ところが最近は、質のいい汗を積極的にかくことで皮膚によい影響を与えると考えられています。
汗の本来の役割には、、、
皮膚の水分量を保ちうるおいを与えてくれる保湿、細菌などから皮膚を守ってくれる免疫、熱を発散させ体温を下げる体温調節があります。
これらを知れば汗をかくことは悪いことではないとわかりますが、汗には、いい汗・悪い汗があります。
いい汗とは、、、小粒で濃度が薄くサラサラで水に近い、またにおいも少なく蒸発しやすいため体温調節を効率的に行ないます。
悪い汗は、、、大粒でミネラルが一緒に排泄され濃度が濃く、嫌なにおいがします。また蒸発しにくく体温調節機能が低くなっています。
汗の本来の役割を発揮するには、汗腺を正しく機能させ、いい汗をかかなければなりません。
いい汗をかくには、、、
①ウォーキングなどの有酸素運動を1日20~30分程度、汗ばむくらいで行なう。
②命を脅かす酷暑のなかではおススメしづらいですが、エアコンには頼りすぎず、設定温度は27度くらいで。温度が低すぎると汗腺が衰えることも。
③入浴は37~38度の半身浴がおススメ。長く浸かれて芯から温まりいい汗が出ます。高温の全身浴では汗腺が働きません。
④入浴直後にエアコンで急激に体を冷やすとせっかく開いた汗腺が閉じてしまうので、体を拭いたらうちわや扇風機で自然に体温を下げ汗を蒸発させましょう。エアコンは汗が出なくなってから。
⑤食事は血行を促進させるショウガや代謝をあげる酢を取り入れていい汗をかきましょう。また女性ホルモンには過剰な発汗をおさえる働きがあるので、似た働きを持つ大豆イソフラボンの摂取もおススメです。
夏の間、意識して過ごすことで、汗腺をしっかり機能させいい汗をかけるようになれば、きっとお肌の調子もよくなるはずです。
※いまの日本の暑さは命を奪ってしまうこともあるので、健康で自立されているかたたちに向けたお話でした。決して無理をせず、参考にしていただけたら幸いです。
2019年7月31日2:44 PMじんましんの仕組み、ご存知ですか?
梅雨入りし高温多湿で不快な季節です。長く続く暑さを思うとうんざりしてしまうことでしょう。そんな気候で疲れやすかったりストレスを感じるかたも多いと思います。こういった状態がじんましんの引き金になりえます。
じんましんが起こる仕組みは、、、
何らかの刺激を受けると皮膚のマスト細胞からヒスタミンが放出されます。このヒスタミンが血管に作用し皮膚のふくらみや赤みを、神経に作用してかゆみを引き起こします。
じんましんの特徴は、、、
★特定の原因は不明で、勝手に発症することがほとんど(原因がはっきりしているのは全体の3割くらい)
★突然あらわれる少し盛りあがった淡紅色の皮疹で強いかゆみを伴なう
★数十分から24時間以内にいつのまにか消えてしまう
★また別の場所にあらわれる、を繰り返す。この繰り返しが6週間未満に治まるものを急性じんましん、6週間以上続くものを慢性じんましんといい、長いと何年も続くことがあります。
原因が明らかなこともあります、、、
❶かぜ薬や鎮痛剤などを飲んで出た
❷ひっかいたり、物にあたったりした部分に出る
❸サバやマグロなど特定の食べ物を食べたあとに症状が出る
❹日光に当たると出る
❺運動や入浴後など体が温まると出る
❻寒いところに行くと出る
❼皮膚が水に濡れると出る、、、など、同一刺激により起きるとわかっている場合には、その刺激を避けることが大切です。
治療について
ヒスタミンを抑える作用がある薬を使います。様々な種類があり、ご自身に合った薬を続ける必要があります。
症状に合わせて医師と相談しながら量を徐々に減らしたり調子の悪い時は一時的に増やすなど、コントロールしながら気長に治療を継続し、ご自身の判断で急に中止にしないようにしましょう。
悪化させないためには、、、
悪化要因は人それぞれですが、一般的には睡眠不足、疲労、ストレス、アルコールや香辛料などの刺激物の取りすぎなどがあげられます。じゅうぶんな休養や規則正しい生活を心がけましょう。
2019年6月11日12:29 PMアタマジラミを正しく理解しましょう
アタマジラミと聞くと、なんとなくイヤなイメージをいだかれるかたが多いと思いますが、不潔にしているからわいて出てくるものではありません。
★アタマジラミの生態★
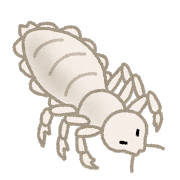
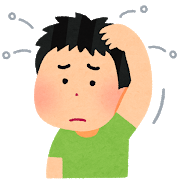
アタマジラミはヒトの頭髪に寄生し、頭皮から吸血してかゆみや湿疹などを起こします。また頭髪に固着した卵を点々と産みつけ、髪の毛にこびりついて取りにくいので簡単に発見できます。
ヒトに寄生するシラミは他の動物には寄生せず、他の動物のシラミはヒトに寄生しません。
ヒトから離れたシラミは運動能力が低く翅もないため飛べません。また、吸血できなくなるため2〜3日で死んでしまいます。
★うつる原因★
決して不潔にしているからではありません。
髪の毛と髪の毛が接触することでうつりますので、頭を寄せて髪の毛が触れあって遊ぶことの多い子どもたちは感染しやすいといえます。帽子やタオルの貸し借りも感染の原因になります。
お泊まり保育やお昼寝のとき、さらに子どもに添い寝する大人も注意が必要です。
★感染予防のために★
頭同士の接触を控え、体に触れるものの共有を避ければ予防になります。ただ、どんなに気をつけていてもお子さま同士の接触をすべて避けるのは困難です。かゆがったり髪に付着物はないかなど普段から気にかけ、早期発見し感染拡大予防につなげましょう。
治療には市販の駆除薬(主にシャンプー剤)を使用しますが、まずは確定診断を含め診察を受けられるとよいでしょう。
2019年3月15日9:55 AM
花粉皮膚炎にご注意を!
そろそろ花粉の対策を考えていただく時期ですが、今回は花粉による皮膚炎についてお話しいたします。
花粉皮膚炎は、花粉が皮膚に直接影響を与えて、かゆみや湿疹を起こす病気です。鼻や目に症状がでる、いわゆる”花粉症”をお持ちでないかたにも起こりえます。
鼻や目に花粉がつくと、くしゃみや鼻水、涙が多く出ます。これは体内に入りこもうとする異物(花粉)を追い出そうとする体のしくみです。同じように、皮膚に花粉がつくと追い出そうとするしくみが働き、かゆみや湿疹などの反応を起こします。
特にお肌が乾燥したり、かゆくてボリボリ掻いてしまうようなかたは、皮膚のバリア機能が低下していて花粉の影響を受けやすい状態にあります。
タオルでこすったり石けんで過剰に洗いすぎるのもバリア機能を損なう原因になります。普段から保湿をして角層を整えておくことが重要です。
予防策は
①スキンケアでバリア機能を補う
②皮膚を清潔に保つ
③マスクやメガネで保護する
④こまめな掃除で花粉を除去する
また、花粉以外が原因の接触性皮膚炎もあります。化粧品、石けん、点眼薬、シャンプーや毛染めなど、顔に触れるものの使用をやめて症状の変化を見極めるとよいでしょう。
もし赤みやかゆみがあっても、掻かないことが大切です。
掻くことで症状は悪化します。
なるべく花粉をよせつけない工夫をして、花粉飛散の時期を乗り切りましょう。
お困りの症状があるときは、お早めにご相談ください。
2019年2月18日6:45 PM
そろそろ春の花粉症対策を!!
まだまだ寒さの真っただ中にある東京ですが、2月中旬には花粉の飛散が始まるといわれており、当院にも内服を開始したいという患者様がすでにいらっしゃっています。去年の3倍近くも飛ぶのではないか?というニュースも耳に入ってきております。
スギ花粉は、飛散開始が確認される少しまえにわずかですが飛び始めるといわれているため、1月のうちから対策を始めるのは決して早すぎることではありません。
花粉症は、症状が出るまえから治療を開始することで、症状を軽くしたり、症状が出る期間を短くするなどの効果が期待できます。2月中旬に飛散開始予報があるため、事前に治療を始めたいかたは2週間まえを目安に開始できるよう準備しましょう。
~治療とともに心がけたいこと~
★外出時にはマスクや帽子、メガネを着用し、上着はナイロンやポリエステルなど花粉の付着しにくい素材を選ぶ。
★帰宅時には、上着にブラシをかけたりはらったりして家に入る。
★目や鼻、ノドを洗う。
★こまめに掃除する。
※花粉症ではない家族の方々にも協力してもらうことが大切です!
これらを徹底することで治療効果をあげることができます。
また、診察の際にはご自身の症状を的確に伝えていただくこと、過去の治療歴とその効果などもきちんと医師に伝えていただくことで、よりよい治療を選択する目安になります。


早めの準備で去年よりも快適にお過ごしいただけたら幸いです。
2019年1月8日6:47 PM
低温やけどを未然に防ぎましょう
低温やけどは、あたたかくて心地のよいものに長時間接することで起こります。温度は40~50℃程度のものです。心地よいため無防備に使いがちですが、油断するとダメージを与える凶器にもなりえます。
お手軽な保温グッズが恋しくなるこの季節、上手に使って寒い冬を乗り切りましょう。
保温グッズのなかでも、カイロや電気あんかのように体に直接あてるものだけでなく、ヒーターやこたつなどの暖房器具でも長時間同一部位にあてていれば低温やけどの危険があります。
低温やけどの場合、熱した油や熱湯に触れたときのような激しい痛みがないため、受傷していることに気づきにくいのが怖いところです。
最初は赤くてヒリヒリする程度でも、1日経過して水ぶくれができてしまった、というような変化が起こります。気持ちよいと感じながらも、長時間あててしまえば熱のダメージはじわじわと皮膚の深部に達し、気づいたときには重症な、治りにくい状態になってしまっています。
~予防するための注意点~
★使い捨てカイロ・靴下用使い捨てカイロ
・貼るタイプのものは必ず衣類に貼り、長時間同一部位への使用は避けましょう。また、貼ったまま眠らないようにしましょう。
・カイロを貼りつけたうえからサポーターやガードルで締めつけると、圧迫により血流が悪くなりやけどが進行する恐れがあります。
・靴下用カイロは靴を脱いだ状態のときや他の部位に使用すると、酸化が過剰になり高温になる可能性があるので注意して使用しましょう。
★湯たんぽ、あんか、電気あんか
・厚手のタオルや専用カバーなどに包んでいても、低温やけどを起こす可能性はあります。早めに布団に入れて温めておき、就寝時には布団から出すようにしましょう。
・足を乗せていると、その部分の圧迫により血流が悪くなりやけどの進行が早まってしまう危険があるのでやめましょう。
★電気毛布、電気敷布
・早めにセットして布団を温めておき、就寝時には電源を切るか、タイマーを1~2時間でかけて、途中で切れるようにしておきましょう。
★電気こたつ
・電気こたつに入ったまま眠らないように注意しましょう。
★ホットカーペット
・ホットカーペットの上で眠らないように注意しましょう。
★ストーブ
・電気ストーブを近くに長時間置かないようにし、つけたまま眠らないようにしましょう。
※疲労感の強いときや飲酒後などは、ちょっとウトウトだけではすまず、眠りこんでしまい、熱さに対する反応が鈍くなりますので注意が必要です。
見た目に変化がなかったり、たいした痛みではなくても、皮膚の深いところで異常が起きているかもしれません。大丈夫だろうと自己判断せず、早めの受診をおすすめします。
2018年12月17日2:46 PM